相談員から患者様へ 医療・福祉の制度のご案内
精神科や心療内科にかかるようになったときに、通院の際の医療費の助成や社会復帰のための訓練など、利用できる制度やサービスが複数あります。利用には条件がある場合や、医師の診断書が必要な場合があります。また、申請に初診日より半年以上経過などの要件があるものもございますので、制度やサービスについてのより詳細な内容については、当院相談員(精神保健福祉士)にご相談ください。
※このページの情報は2023年4月現在のものです
 医療の制度・サービス
医療の制度・サービス
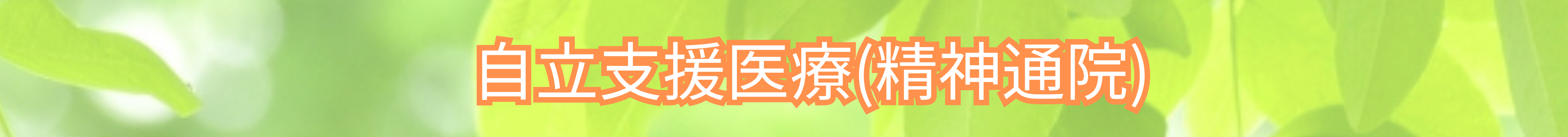
| 制度の概要 | 申請時に指定した医療機関と薬局で、 医療費の自己負担額が1割になる制度です。 (ただし、入院では利用できません。) また、指定医療機関等での精神科デイケア、訪問看護等でも利用が可能です。 1年ごとに更新が必要で、 2年に1度は、更新時に診断書が必要になります。 精神障害者保健福祉手帳を同時申請、もしくは更新される場合、精神障害者保健福祉手帳用の診断書のみでの申請、更新が可能な場合もあります。 また、市町村によっては、残りの1割分の自己負担に対しての助成が受けられることがあり、 自己負担がさらに軽減されることがあります。 詳しくは厚生労働省の公式ページ、愛知県の公式ページ、またはお住まいの市町村の公式ページをご覧ください。 |
|---|---|
| 対象となる方 対象となるサービス等 |
精神疾患を有する方で、 通院による精神医療を継続的に必要とする方 外来診療、 外来での投薬、 精神科デイケア、 精神科訪問看護など |

| 制度の概要 | 一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、 取得すると税金の控除減免などを 受けられたり、 障害者雇用枠での就労が可能になる制度です。 また、地域によっては医療費の助成、 公共施設の入場料等の割引、公共交通機関の運賃の割引、福祉扶助料の支給などのサービスを受けることが出来ます。 障害年金を受給している方は、診断書無しで年金証書の写しで申請することもできます。 その場合は、 等級が受給している障害年金と同じになります。(例:年金2級の場合、手帳2級) 申請には、対象の精神疾患の初診日から6ヶ月以上経過している必要があります。 有効期限は交付日から2年で、更新時には診断書もしくは年金証書の写しが必要です。 詳しい情報は、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターのこころの情報サイトを ご覧ください。 |
|---|---|
| 対象となる方 対象となるサービス等 |
精神疾患(発達障害・てんかんを含む) により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があり、その精神疾患の初診日から6か月以上経過している方 税金の控除減免、福祉扶助料の支給など(自治体により異なります) |
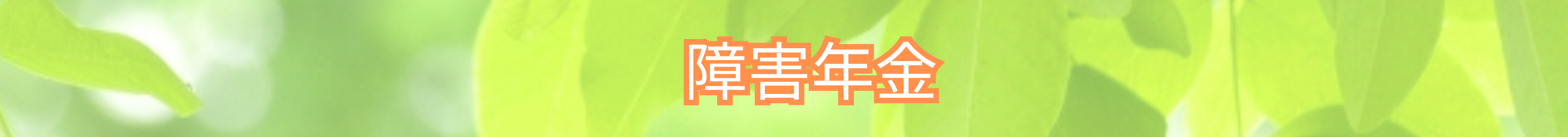
| 制度の概要 | 病気や怪我によって生活や仕事等が制限されるようになった場合に受け取れる年金です。 年金の支給額は年度ごとに変動します。 また、収入が一定以下の人には、年金生活者支援給付金が上乗せして支給されます。 精神障害による障害年金の認定は有期認定であることが多く、受給できる期間は人それぞれ異なりますが、多くの場合1年~5年で更新が必要になります。 更新には診断書の提出が必要です。 詳しくは日本年金機構の公式ページをご確認ください。 |
|---|---|
| 対象となる方 | 一定の障害状態にあり、年金に加入している期間に初診日がある方、 または初診日が20歳より前にある方 ※受給には保険料の納付要件などがありますので、ご自身が障害年金を申請できる要件を満たしているかどうかをお近くの年金事務所や市役所等の担当窓口でご相談されることをお勧めします。 |
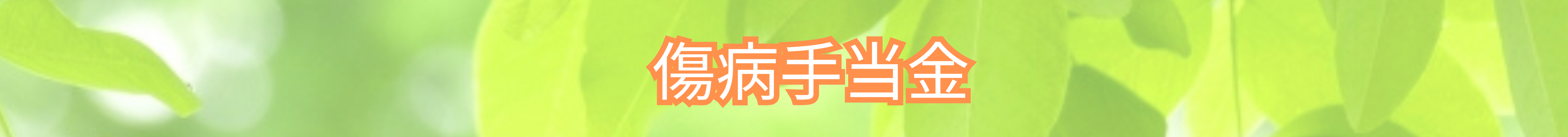
| 制度の概要 | 病気や怪我により仕事を休んだときの生活の保障のための制度です。 支給開始から通算で1年6か月に達するまで、休業した日の分が支給されます。 申請書には、本人、事業所(勤め先)、医師の記入が必要になります。(費用は保険適用) 詳しくは全国健康保険協会の公式ページや、ご加入の保険組合のページをご覧ください。 |
|---|---|
| 対象となる方 | 健康保険の加入者で、下記の条件をすべて満たす方。 ・業務外の事由(=労災の対象外)での病気、怪我の療養で休業した ・医師などにより労務不能と判断された ・休業期間中に給料の支払いがなかった、または支払われた給料が傷病手当金の額より少 なかった ・連続した3日間を含む4日以上休業した |

| 対象となる方 | 精神科に通院されている方 |
|---|---|
| 概要 | 精神疾患のある方の、生活リズムの改善、対人関係の訓練、社会復帰の促進など、社会生活機能の回復のための通所型リハビリテーションです。 デイケアで実施されるプログラムは様々で、料理や運動、創作活動、ソーシャルスキルトレーニング(SST)等や各種年間行事、復職を目指す方向けのリワークプログラムを実施しているところもあります。当院では、主に小学生~高校生を対象とした児童思春期デイケアを開設しており、院外活動や学習支援にも力を入れています。 精神科デイケアのスタッフは、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師等の専門職で構成されています。 精神科デイケアの利用料には実費分を除き保険が適用され、医療費助成が利用できることもあります。 ご利用にあたっては、まずは主治医にご相談ください。 |

| 対象となる方 | 当院に通院されている方 |
|---|---|
| 概要 | 医師の指示のもと、看護師、作業療法士、精神保健福祉士といった専門職がご自宅等に訪問し、制度利用のお手伝い、お薬の管理のお手伝い、リハビリテーション、家族関係の調整等の支援を行います。 当院では、医師の判断により当院のスタッフが実施する場合と、地域の訪問看護ステーションに委託して実施する場合があります。 精神科訪問看護の利用料には、実費分を除き保険が適用され、医療費助成が利用できることもあります。 ご希望の方はまずは主治医にご相談ください。 |
 福祉の制度・サービス(例)
福祉の制度・サービス(例)
放課後等デイサービス
(放デイ)

障害を持つ6歳~18歳の就学児童、生徒の方が対象の福祉サービスです。子どもの状況に応じて、集団プログラムや個別プログラムを実施し、子どもの健全な育成をはかります。当院では、隣の建物でよろここデイサービスを開設しています。
ご利用にあたっての詳細はお住まいの市町村の窓口やホームページ等でご確認ください。
グループホーム
ショートステイ

グループホームは障害のある方々が複数人で共同生活をし、スタッフによる生活面のサポートを受けながら自立を目指す共同住宅です。
ショートステイは、障害のある方のご家族が冠婚葬祭等で家を留守にするとき、病気や怪我をしたとき、休息が必要な時などに一時的に障害のある方が施設に入所し、介助や支援を受けることが出来るサービスです。
障害福祉サービス事業所
(訓練系)
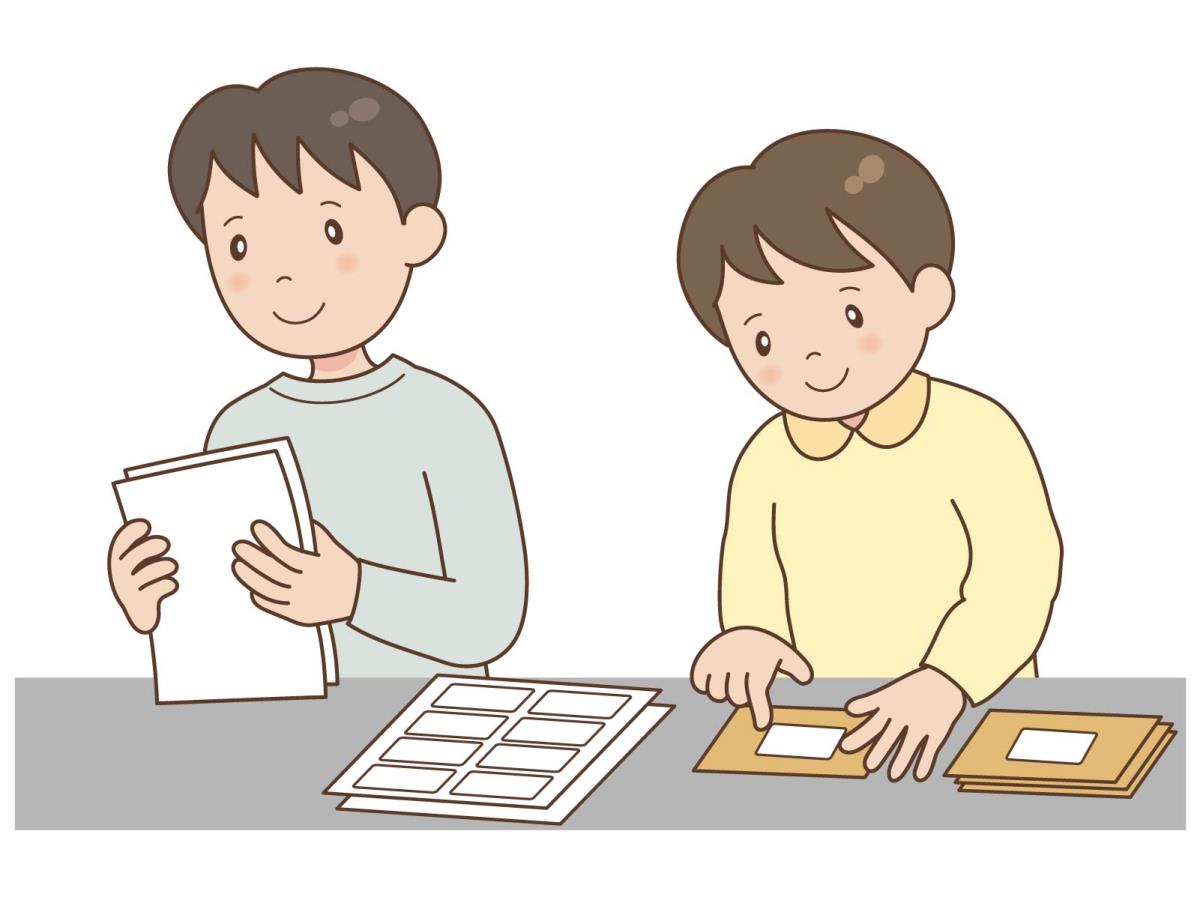
日常生活の中で必要な能力の維持や向上を目的とした生活訓練や、就職のために必要な知識やスキルの向上を目的とした就労移行支援、障害のある方の働く場所としての就労継続支援(A型・B型)など、様々な目的やニーズに応じた多様な事業所があります。
生活訓練や就労移行支援の利用期間は原則として2年間です。
その他の福祉サービスについてや、各サービスについての詳細は厚生労働省のページをご覧ください。
上記のような福祉制度・サービスの利用には、お住まいの市町村が交付する受給者証が必要です。
受給者証の交付には、各種障害者手帳や自立支援医療受給者証(精神通院)が必要になります。
市町村ごとに異なる場合があります。詳しくはお住まいの市町村の窓口、もしくはホームページ等でご確認ください。
9:30~12:30 / 15:00~18:00
休診日 : 金曜日・日曜日・祝日 または メールでのお問い合わせはこちら

